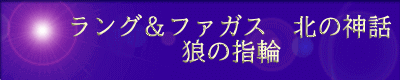
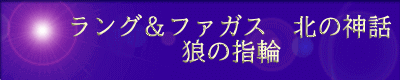
大いなる森の老婆は泉のほとりにたたずんでいた。
ミーミルの泉は、いまやその魔法の力のすべてを失って、ただの泉と化してしまっていた。不思議な活力に満ち溢れていた泉の、死そのものを思わせる静謐。大いなる森の老婆はそれが悲しくも恐ろしかった。
魔力が消え去れば、世界の終わりを演出した泉とて、魔法を失うことに例外ではない。この状況はあらかじめ理解していたことだった。しかしそれでも大いなる森の老婆の心を冷やすのには十分であった。
膝がひどく痛む。泉が放つ、若さの魔法の効果が消え去ってしまっているためだ。体の他の部分も徐々に年齢に相応しいものとなってゆくだろう。この状態が長く続けば、最後は全身痛みの塊となって死ぬのだ。
泉の水は澄み切り、底に転がる眼球がよく見えた。それは泉の水が湧きだすのに合わせて、ゆらゆらと揺れてはいるが、今までのように独りでに動くことはない。
神の目玉だから腐りはすまい、と老婆は誰に言うともなくつぶやいた。
しかし、その神々だとて、いまは自分たちの領地の中で、息も絶え絶えに冬眠しているだろうとは、老婆にもわかっていた。魔力の飢餓。いかに神々の生命力であろうとも限界はある。
老婆は空を見上げた。昼の月だ。もはや月が夜に輝くことはなくなっている。かろうじて昼だけは、その姿を見て取ることができる。しかしその色は冴えた青白色ではなく、隠すところなき金色だ。
フェンリル狼もその魔法の力を失い、ゆっくりとした飢餓の中にあるのだ。世界を食らう元気はすでにない。あの狼は目の前に転がる金の指輪の洪水をどう感じているのだろう?
そもそもあの巨狼を倒す目的で、今回の作戦は立てられたのだ。まさに捨て身の一撃。だがこうなってみると、たとえフェンリル狼が解放されることになっていたとしても、世界が元のままの姿だったほうがよかったのではないかと、あらためて後悔の念が巻き起こってきた。
大いなる森の老婆は、泉に貯えられた知識から、この世界の歴史の真実の姿を知っていた。
太古のあの時代。
神話が予言するところによれば、神々と巨人の戦いは、やがて世界を破滅へと導くラグナロクの時へと至るはずであった。そして九つの世界は一端破滅し、再生の時を経て世界は一新され、新しい時代が始まるはずであった。
新しい神々と新しい人々による、理想郷の時代がだ。
だが、どこかでそれが狂った。
人間が賢くなり過ぎたのだ。
予言の成就を否定し、再生できない形で世界を破滅させたのは、神々でも巨人たちでもなく、ちっぽけな人間たちだった。
ルーン魔法の秘密を解き、人間たちは繁栄した。微妙な均衡の上に成立していた魔法世界を、その爆発的な成長により覆してしまったのだ。
かってこの世界に栄えた古代魔法王国の数々。あの魔法大戦の最中に、ドラウプニルの腕輪は輝ける空飛ぶ船に載せられて、敵の領地に投げ落とされた。魔法を失い、自身も墜落する空飛ぶ船の姿。空虚な静かさが世界に広がり、その中で逃れようもない窒息が始まった。世界を再生させるために大事に王宮の中に保存されていた魔法の箱は、その直前に最大級の炎の武器を受けて消滅していた。
大いなる誤算。唯一の救世主の消滅。
世界樹は揺らぎ、変形した。その梢は九つの世界を支えきれなくなり、力を失った枝には亀裂が入った。勢いを失った月は、スコールとハティの二大巨狼に追いつかれて食われ、その巨狼も自らを貪り尽くして死んだ。
そのときだ。この大変動により、自分をつなぐギョルの丸石ごと、フェンリル狼が空に投げあげられたのは。
こうして新しい月は誕生した。
だが、これらの破滅は再生を産み出さない、本当の破滅であった。慎重に組まれていた予言の魔法は消滅し、世界樹は枯死への道を歩んでいた。世界の崩壊はとどまることを知らず、不毛という名の死神が静かに、そして着実にその勢力を広げていった。
創造者ライドがマナ創世の魔法とそれに必要な魔力を携えてこの世界にやって来なければ、九つの世界のすべては滅びの道をたどっていただろう。
これこそが始祖問題の解答。
老婆はそれを知っていた。魔術師たちが永遠の議論を繰り返しても結論が出ることは有りえない。それは外の世界から持ちこまれたものなのだ。九つの世界を取り巻く炎と霧の向こうから、創造者ライドにより持ちこまれたものなのだ。
ライドは魔法世界を再生させた。ミッドガルド界を統一し、人間を組織し、再編成した。行きすぎた魔法の使用を制限するために、勢力が三分された形の魔術師ギルドを作った。
そしてその裏では、ミーミルの泉を設置し、森の老婆たちによる世界監視体制を作り上げた。その目的は、今度こそこの魔法世界を正しい予言の流れに載せること。たとえまた破滅が訪れるにしても、それは再生を伴うものでなくてはならない。
大いなる森の老婆は、心の中から夢想を断ち切った。
ファガスがこの世界を救う鍵である魔法の小箱を持っていることは、泉の予言で知っていた。だが敢えて、大いなる森の老婆はそれを彼らにゆだねたままとしていた。
予言に携わる者は、この世界の運命に、自ら積極的に関ってはならないのだ。
ミーミルの泉の予言能力を強めたときに、創造者ライドはそう規定していた。あまりに泉の力そのものが世界に関ると、それは自分で自分の予言を否定するという自己矛盾を引き起こすことになる。
世界を滅ぼすのも、そこに住む者の意思ならば、世界を救うのも、そこに住む者の意思でなくてはならない。基本的には世界の傍観者である泉の老婆たちが、それを完全に制御することは許されていない。
今回ばかりは例外だったのだ。フェンリル狼の危機が近づいていたのだから。
ラングとファガスが魔法の箱を開き、世界をふたたび元の姿に戻すであろうことは、予想がついた。だが確信ではない。
ファガスの家に行き、箱を開けるように示唆することは簡単だ。だがそうすれば、予言者が予言の実現にじきじきに手を貸すことになる。そうして始まる世界はミーミルの泉による一極支配の世界だ。早晩、それは完全なる滅亡の様相を示し始めるだろう。
これ以上、手を出すことは許されない。大いなる森の老婆はそう決意していた。
他の泉の老婆たちが、大いなる森の老婆のこの考えを知ることはないだろう。魔法が失われた今、動かぬ泉を前にして、彼女たちはただひたすらに、世界が再生される瞬間を待ち続ける以外には手がないのだ。
もう一度、泉の中の目玉を見つめる。
泉の水はとても冷たい。雪解け水が噴出したものなのだから。神々が死に、この目玉が神の肉体の一部としての特権を失ったとしても、この冷たい水の中では腐ることはないだろう。それはただ、静かにその意味を失うだけなのだ。
このままでは、世界もこの目玉と同じ運命をたどる。
アスガルド、ミッドガルド、ヨーツンヘイム、ニタヴェリール、アールヴヘイム、スヴァルトアールヴヘイム、ヘル、そしてニヴルヘイム。世界樹が支えるこの広大な世界たち。
世界樹そのものが魔法によって生きている木なのだ。その枝はいまきしみ音をあげて、折れかけている。ミッドガルド界を支える基盤にひびが入りかけているのだ。
ここから先は予想がつかなかった。ある日、突然、青空に亀裂が走るのか。それともただ、あらゆる植物が枯れ果てるのか。
森のあちらこちらに出没していた魔法生物は姿を隠し、その代わりに野犬の群れが我が物顔に走りまわっている。世界の様相からその輝きが失せ、厳しい現実だけが浮き彫りとなり始めている。
これだけでもあたしに取っては、十分に世界の終わりだよ。そう老婆はつぶやいた。
ここまでくれば、すべては運命の女神たちの意思一つ。世界樹とは、あらゆるものを内側に含んだ、大いなる生物なのだ。人間の自由意思も、運命と存在と必然が巻き起こす大いなる渦と円環の中にある。
ラングとファガスは自分たちの意思で魔法の箱を開けるのだが、それもまた予定調和の上にあるという、この矛盾。
大いなる森の老婆は、運命について深く考えこんだ。世界という名の牢獄の暗闇の中で。
どれだけの時間が経っただろう。
何かが周囲を駆け抜けて行った。
目には見えないものが、透明な空気を抜けて、叫びを上げたかのように。
泉の表面に細波が走る。まるで泉の生命が、かぼそいため息をついたかのようであった。いきなり風が甘くなり、大気が踊る。木々がざわめき、命のきらめきを放ち始める。
大いなる森の老婆は顔を上げた。
森の中から無音のどよめきが湧き上がる。魔法の彩りがその上に吹き上がった。
「いやだよ。あたしゃ」老婆は目を拭った。
「もうずいぶんと長い間、泣いたことなんかなかったのに」