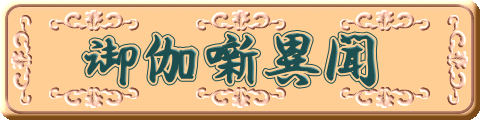
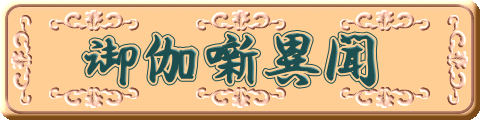
降り注ぐ月の光りの中、幻想的な川の眺めの上を船は滑べっていった。小さな屋形船の舳先には船頭が一人立っている。静かな川の上を波も立てずに、ただ月の光りのみを友として、船頭の顔はひとつの彫物の様に見えた。
ふと気付くと、川の岸に女が一人立っている。年の頃は十六ぐらいか。月の光りの中で長く伸びた女の髪が美しく流れた。船はすいと近付いた。
先に声を掛けたのは船頭の方だった。
「申し、そこの姫様。この様な夜更けにどうなさいました」
女が答える。鈴を振るような声とはこういうのを言うのだろうか。
「なんでもありません。月が余りにも奇麗なので、眺めていた次第です」
「それはまた、風流な心がけだが。お気をつけなさい。ここらでは最近よく神隠しがおきますのでな」
「神隠し。そのようなものは恐れはしませぬ。やがてはこの故郷を離れる身の上では」
「そのような。どこぞへと旅でもなさいますか」
「見知らぬお方に話すようなことでは御座いません。どうか、私めのことはお気になされませぬように」
「そうは言われましても、やはり気にかかりますでな。神隠しのことは事実で御座います。見れば高貴なる姫様と思います。このまま行ってしまって、貴女様に何事かあれば、わたくしめに類が及びます。せめてお供なりとつけてお出になりませ」
「お供ならばついております」
軽やかな笑い声。何の含みもない、ただ笑うために生まれたような純粋な笑い声。
「どこに?」
「あそこに」
たおやかな手は天に輝く月を指した。
「また、馬鹿な事を。神隠しとはいうても、その実はどこぞの野盗めが人さらいをやっているもの。もしこの私めがその野盗ならばいかが致します」
またもや姫が笑って、答えた。
「あるいは、どこぞの妖かしめが神隠しに見せて、人を喰ろうておるのでは。もし、この姫がその妖かしならばどうなさいます」
その言葉に驚いたのか、船頭の体が揺れ、船がザブリと波を立てる。
「これはまた異なことを、妖かしなぞとからかうとは。そのようなもの、今まで私は見たことがありませぬ」
「己以外は、ということですね」
またもや船がザブリと揺れ、船頭がへたへたと崩れ折れる。その体が縮むとただの抜け殻へと変ずる。
船が水の中からのそりと立上り、舳先が割れて夜目にも赤いと思われる舌がべろりと垂れた。今まで隠れていたからだが船の底から現れる。船の形をした頭の両脇にいくつもの目が現れる。
「何故? 判ったのか? 見れば普通の人の様だが」
「そのようなこと、どうでもよいではありませんか。月夜に船とは良き姿でしたが、こうなっては興が覚めたというもの。行っておしまいなさい」
「いや、見逃すわけには参らぬ。神隠しを恐れて近頃は夜歩きをする者もおらん。
お前の様な美しい姫はそれなりに旨かろう。お前を最後に、他の地へ移ろう」
「お供がいます。私めには手も触れられませぬ」
「どこにもそのような者はおらん。人の気配は他に無い。」
妖怪は笑った。妖怪の頭を成す船がバカリと二つに割れ、尖った歯の並びがあらわになった。
妖怪はぐいと姫に近付いた。そのとき、天空遥かにかかる月から、一筋の光りの矢が放たれ、妖怪の背中に突き刺さった。
「!?」
訳も判らず、水面に血の泡を立てて妖怪は没した。
しばらくは水面に波が立っていたがそれもやがては収まり、後はただ静かに月を映すのみ。
「姫、姫よ」
歳を取った翁が一人、明りを手に呼ばう。
「か弱い姫が一人で、このような所に月を見に来るなど。婆に聞いてわしは肝が潰れるかと思うたぞ。明日は帝がお見えになる日じゃ。眠れぬ気も良う判るが、ささ、家に帰りましょうぞ。この辺りでは良く神隠しが起るそうじゃ。折角、神様にもろうたお前じゃ、神隠しになぞ会ってもろうては困る。ささ、家に帰ろうぞ」
何がおかしいか良く笑う姫を連れて、翁は家に帰った。
かぐや姫。月からの迎えが来るまで、後三日。