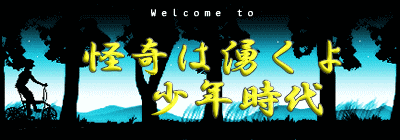
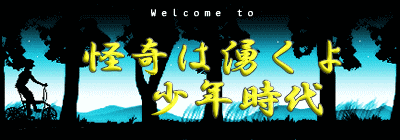
母は大手の土建会社の経理部に嘱託扱いで務めていたので、決算期ともなると夜遅くまで残業となるのが通例であった。もちろん経理部のその他の面々も同じく残業である。
決算期がすぎるとそれまでの騒ぎが嘘のように静けさが訪れる。連日連夜残業していた部員は皆、定時退社のシフトへと戻る。
ただ一人を除いて。
経理部の中でも新人に属する若い男の子である。
「仕事無いでしょう? 帰らないの?」
不思議に思った母が尋ねる。
やることもなくぼうっとしていた男の子が慌てて応える
「あ、僕、寮なんで門限があるんです。夜七時になるまで帰れないんです」
逆さ門限である。
その子が配属された寮は、山の麓にある竹やぶの中に作られた一件の家を改装したものであった。
この家一軒にはだいたい四人か五人、新人が割り当てられる。大きなリビングが中央にあり、かなり豪華な部屋がそれを取り巻くように配置されている。元は大家族用の家で、無人となったそれを買い取ってそのまま会社の寮にしたものである。この辺り、土建屋は色々と話が転がりこみやすい。
家は竹やぶに囲まれていて、昼でもやや薄暗い。外界から隔絶されたようなと表現すればぴったりかも知れない。
お約束通り、死人が出た。
自殺である。新人のうちの一人が大きなリビングの真ん中で首を吊った。
「それからね。出るんです」男の子は続けた。
リビングに置かれた大きなテレビの背後に、首を吊った男の幽霊が立つ。それも100%の確率で、必ず出るのである。出現した位置からは動かず、ただ恨めし気に見つめるのである。
もちろん他の新人たちは寮を代えてくれと会社に訴えたが取り合ってくれない。お祓いもしてもらったが効き目がない。
みな頭を抱えた。
だが、ただ一つだけ、救いもあった。
「彼が出るのはこちらが一人のときだけなんです」
生きている人間が一人のときという意味だ。生きている人間が二人以上揃うと、幽霊は出ない。
そういうわけで寮には門限が設けられた。先に帰った人間は、竹やぶの入り口の所で待つ。他の誰かが帰って来たら、一緒に連れだって中に入るのである。そうすれば幽霊は出ない。
こうして逆さ門限は成立した。
「ご苦労さま。お先に失礼します」
若者を一人残して、さらりと母は帰った。家にはお腹を空かせた子どもたちが待っている。幽霊話に付き合う余裕は母には無い。