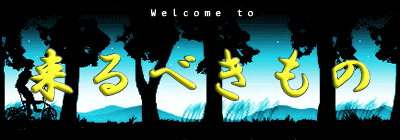
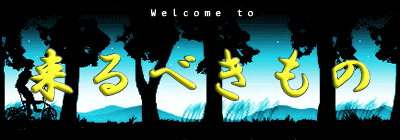
近くのバーでときどき占いを開業する。見料はカクテル一杯。
二人連れの女性が相談に来た。
「家の中で毎夜毎夜変な音が聞こえるんです」一人が話し始める。
あの~、私、霊能者じゃ無いんですが。
世の中には、占い師と霊能者の区別がつかない人が多い。霊感占いなどというものが流行ったせいだろうか?
例えるならば霊能者は水の下のクジラを直接ソナーで捕えることができる人であり、占い師は水面の波紋からクジラが次に浮かび上がる場所を予測する人である。霊能者は能力、占い師は技術である。
「でね、二階に上がる階段の真ん中辺りでパタパタパタパタ何かを叩く音がするんですう」
女性は続けた。
困った。聞いてくれない。
「それはね」連れの女の人が口をはさんだ。
「階段の途中に白装束の着物来た女の人が横向きに浮いているの。両手両足が折れていて、それで手足をばたばたするの。その手足が壁に当たって音がしているの」
ええっと。もしや貴女、見える人?
そうらしい。
「信じてくれる?」
嘘の可能性はあるけど、取りあえず信じます。こちらも色々と見て来ていますから。
占ってみた。占うまでも無いが。
すでに大体の背景は推測できた。
横向きになった女の人。なぜ、空中で横向きに?
それは死んだときに横向きだったから。恐らく、水死だ。手足のバタバタは必死に泳いでいるのだろう。
二階への途中という中途半端な高さに出るのは、死んだときの水面がその高さだったからだ。
ローマ時代の軍団の幽霊の目撃例では、足首が十五センチ地面に沈んだ状態で行進していたという。千五百年の間に、土や砂が積り、地面が十五センチ高くなったせいだ。周囲の環境は変化しても、律儀に昔の高さそのものの道を歩いている。幽霊とはときたまこういうことをする。認識能力の一部が見事に欠けているのか、あるいはまだ昔の時代の夢の中に生きているのか。
このケースも同じで、死んだときの水面が一階と二階の中間だったのだろう。この辺りは昔は穀倉地帯であった。水田地帯を住宅地にするために地下に滞留した水を抜くと、地面は沈み込む。そのため、昔の水面は現在の人間の頭の高さより上になる。
だが、白装束を着ていること。そして両手両足が折れていること。この二つは、事故で死んだのではないことを示している。恐らくは逃げられないように両手両足を折られてから溜め池に投げ込まれた。
儀式としての殺人。人身御供だ。
そんな風習があること自体、死んだのは江戸時代ということになる。豊穣の儀式か、雨乞いの願いか、この地の水神に捧げられたのだろう。だからこそ、ただの幽霊なのに神格化し、これだけの歳月が経っても普通の幽霊のようには消えていない。音を出せるだけの力がまだ残っているのがその証拠だ。
死んだ後に巫女としての属性を帯びたのか、あるいは元々の巫女を生贄にしたのか。「神の嫁」という考え方だ。巫女が初潮を迎えると、神への捧げものにする。
惨い風習。神に捧げるならまずそれを命ずる自分の命であるべきだろう?
それが姿を現すまでではないが、少なくとも普通の人に聞こえる音を出すところまで来ているということは、その水神が次の生贄を求めているということになる。すでに溜め池も潰されてしまったろうに、それでも生き延びるために、タタリ神となってエサを求めている。
嫌な話だなあ。
「すぐにその家を出なさい」思わず言ってしまった。「死人が出ます」
これは失敗であった。
「死盗姦」は占わず。これは占い師の鉄則だ。特に死を占わない理由は切実だ。それは死を占い、それを聞いた質問者が死を回避した場合、代わりに冥界の役人に占い師の命を差し出すことになるというものだ。
カクテル一杯で占う、積徳のための行で、見知らぬ人間のために自分の命差し出すバカがいるものか。
だが、まあ、言ってしまったからにはもう取り消しはきかない。
「でも、最近旦那が鬱病みたいなっちゃって、家を出るなんてできないのよ」
自分がどれだけのものを差し出されたのか判っていない女性が愚痴る。
「私の占いはここまでです」
まずったなあ。さてさてどうなりますことやら。
数か月経って、見える方の女の人がまた飲みに来た。
「あれ、どうなりました?」
当然の質問をしてみた。
「それがね。あの一か月ぐらい後に、あの子の義理の父親が浴槽の中で溺死しちゃったの」
ひえええ。
その後、話を聞いたその旦那の方が、占い師の居所を訪ねていたそうだが、結局現れることは無かった。
「最近、何だかあの子鬱病になったみたいで没交渉になっちゃったのよ」
うーん、憑依が原因か?
つまるところ、タタリ神は次の獲物を自分の縄張りである家の中に確保しているわけだ。
この事件は最後には何故か、義父が死んだのは、見える子が幽霊を霊視したからだという話に化けることになった。
「全部私のせいなんだって」
彼女はそっと不満を漏らした。
もちろん、彼女は何もしなかったわけではない。当の女の子に頼まれて、その家に結界を張りに行ったそうだ。だが、私の奨めに従って、問題の風呂場にだけは結界を張らなかった。結界をあまりきっちりと作ると、閉じ込められた相手が暴れて、結界の消耗が早くなるためである。いかなる封印も長く持つものではない。風呂場の結界を張らなかった代わりに、ここは危ないから気をつけるようにと言い渡しておいた。
すべては無駄だったわけだ。人間という者は警告を聞かない。たとえ自分の命がその警告に掛かっていても。
さらに後日談が少しだけある。
すでにその友人との縁が切れたある日、その白装束の女の人が見える女の子の家を訪れた。
どうやら手持ちのエサを食い尽くしたらしい。タタリ神の水先案内人としてこの白装束は付近の空中を泳ぎ回っているようだ。少しでも縁が生じたらそれを手繰って次のエサへと向かう。
いきなり食べたりはしない。まず音などで注意を引き、縁を深くするのが先だ。私はこれを「道を開く」と呼んでいる。
このようにまず先ぶれを見せるのはエサが安全かどうかを確かめるのが目的だ。人間の中には強い霊能力を持つ者の他にも様々な地雷がいる。ある者は強い先祖を守護霊としてつけている場合があり、ある者は宗教教団の中心に知り合いがいたりする。これらの背景は突いてみないとわからない。だからそれを確かめるために白装束の女などを使うのだ。
軍事用語で言う威力偵察。ハチの巣を突いてみてハチがどのような行動に出るのかを確かめる。
もちろん祟り神の強さによってはこれらの防御を突破することもできる。だが食べれば面倒な者を食べるよりは、もっと防御の手薄な者を探した方が遥かに良い。神々というものは例えそれがタタリ神でも計算高いものなのである。
見える彼女のケースは彼女の家に纏わる強い守護神が現れ、白装束の女を追い払って一件が落着した。
私のところには現れなかった。ただの占い師など、いったい誰が気にするというのか。