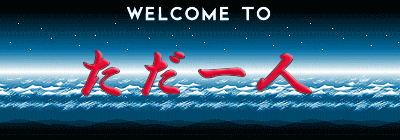
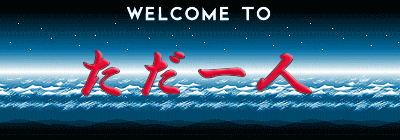
母が死んで初めての正月。朝の三時にピンポンで起こされた。
「へ~い」
取りあえず返事だけして、ベッドから降りる。
誰だよ、元日の朝から。宅配便? あり得ない。年賀状? もっとあり得ない。
もう一度ピンポンが鳴る。この家のドアベルは無駄に音が大きい。
「へ~い」
もう一度返事をしてからドアノブに手をかけてから固まった。
実際のところ、元日の朝三時に訪ねて来るような、どんな用事があるというのか?
尋常な話ではない。そこで初めて、ドアスコープから外を覗いた。思ったとおりに誰もいない。
このとき住んでいたマンションはビルの入り口にパスワード式のロックがあり、ビルの1フロアにつき、1世帯分の部屋しかなかった。五階建ての内、一階部分は倉庫であり、二階に私が住んでいて、三階から五階まで誰かが住んでいるが、彼らは滅多に顔を合わせることもない住人たちで、おまけにピンポンダッシュをしそうな人はいない。子供のいる世帯はいないし、大人でピンポンダッシュをしそうな変な人間もいない。そもそも階段を昇り降りする足音なしにここでピンポンダッシュなどできはしない。
でも待てよ、と思った。今日は母が死んでの初めての正月。
そうか! 帰って来たんだね。
ドアの向うでじっとドアが開くのを待っている母の絵が頭に浮かんだ。
待ってて、母さん、今開けるから。
もう一度ドアノブに手をかけて、また動きを止めた。
もしドアを開けた先に死んだ母がいて、もしそれが母に似ているが母でない何かだったとしたら。
怖い想像が浮かんだら、もうドアを開けることはできなかった。
そっと鍵をかけ直し、足音を殺してベッドに戻ると、朝まで寝た。朝日の中でドアを開けてみたが、当然そこには何もいなかった。
私はあの時、ドアを開けるべきだったのだろうか?
そうするのが愛というものだったのだろうか?